- Home
- ハラスメントの予防と対策サービス一覧
- パワハラ対策(パワーハラスメント対策)
ハラスメントの予防と対策サービスパワハラ対策(パワーハラスメント対策)
パワハラ対策(パワーハラスメント対策)でやるべきこと
企業がパワハラ対策でやるべきことは、具体的には以下の3つがあります。
- (1) パワハラについての方針明確化と従業員への周知・啓発
例)トップメッセージの発信・教育研修・各種取り組みによる意識啓発 - (2) パワハラの相談に対応するための体制の整備
例)相談窓口・相談体制・相談担当者の教育 - (3) パワハラの相談を受けた際の迅速かつ適切な対応
例)相談対応・ヒアリング・被害者/加害者への対処
これらのパワハラ対策は今日、企業において「やらなければならないこと」として認識されており、対応に尽力されていることと思います。
パワハラ対策の目的
なぜこれらの対策をやらなければいけないのか。対策理由について次のように理解を深めたいと思います。
パワハラ防止法と呼ばれる「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(以下、労働施策総合推進法)」の第9章「職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して事業主の講ずべき措置等(第三十条の二―第三十条の八)」は、2022年4月には、すべての企業を対象に法制化されました。
パワハラ防止が付記された「労働施策総合推進法」の第1条には次のように書かれています。
この法律は、国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、労働に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生活の充実並びに労働生産性の向上を促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、経済及び社会の発展並びに完全雇用の達成に資することを目的とする。 (太字は弊社による)
※出典:労働施策総合推進法
この条文から、主要なキーワードとして以下が抽出できます。これらがパワハラ対策の目的です。
- 労働市場の機能の適切な発揮
- 労働生産性の向上促進
- 労働者の能力発揮
- 労働者の職業の安定・経済的社会的地位の向上
- 経済及び社会の発展
- 完全雇用の達成
これらの阻害要因になるからパワハラ防止は必須だと考えられています。企業のハラスメント対策は、「とにかくパワハラをなくす、撲滅する」方向へ邁進しがちです。しかし、本来の目的は、労働者の能力発揮や労働生産性の向上といった、事業推進のために必要不可欠な要素を確保し、実働させるため、つまり、企業活動を発展させるためなのです。
パワーハラスメントの現状
加えて、精神障害の労災認定基準については、2020年に「パワハラ」が認定項目として追加されており、業務災害に係る精神障害の出来事別決定及び支給決定件数では、「パワーハラスメントを受けた」が以来、増加傾向にあります。(令和2年度180件、令和3年度242件、令和4年度257件、令和5年度289件、令和6年度389件)
こうしたことから各事業所では法的にも、本来の事業目的の観点からも、段階的・継続的なハラスメント対策が求められているのが実状です。
また、世界に目を向けると、2021年6月、職場でのセクハラやパワハラなどハラスメント行為を禁じる初めての国際労働機関(ILO)条約が発効。日本政府は批准に消極的であったものの、世界の動きは看過できず、グローバル社会において、ハラスメント対策は日本企業がもはやおろそかにはできない取り組みです。
2001年にパワーハラスメントということばを弊社が考案し提唱して以来、その概念が日常に浸透する一方で、パワハラ(パワーハラスメント)に対する認識や解釈はますます多様になっています。正当な指示や注意をパワハラと訴えられ、困惑する管理者も増えています。
そのような中、私どもはハラスメント対策のパイオニアとして多数の企業にハラスメント対策支援に関するコンサルテーションをさせていただき、お客様の現状に合わせてパワハラ対策の課題にお応えしてまいります。
パワハラ対策でやるべきことは、段階的・継続的な取り組みです。
-
やるべきこと その1: パワハラ対策の“はじめの一歩”
パワハラ対策は、まず社内規則にパワハラ防止策を盛り込み、トップメッセージを発信することから始めます。法律に則ってすでに盛り込まれているセクハラ(セクシャルハラスメント)やマタハラ等の規定を合わせて、パワハラについても社内規則の制定・ガイドラインの配布をすることで、パワハラに関する認知を高め、社内へ周知徹底しましょう。パワハラ防止法が策定してから数年経っていることから、規則への明記は済んでいる企業がほとんどと思います。その場合は、トップメッセージの発信から始めてください。
-
やるべきこと その2: 全社員への浸透
トップ層から順に管理職、一般社員、非正規やパート社員も含め、網羅的に教育研修を実施していきます。教材(ガイドブック、研修動画、e-ラーニングなど)を活用したり、職場アンケートの実施を通じて実態を把握し、継続した啓発活動につなげることも重要です。
コミュニケーション活性化のために、従業員一人ひとりの意識や行動の変化を促す取り組みを実践しましょう。
ガイドブック、小冊子、研修動画、eラーニングなど -
やるべきこと その3: 常に最新の情報提供を
ハラスメントに関連する施策の法制化は頻繁に行われています。
こちら↓のページの「該当する法律」をご確認ください。
・ハラスメント対策と企業の責任
当HPでご紹介しているパワハラ関連のニュースや判例解説、ハラスメントに関する調査研究等を参考に、情報を定期的に提供したり、教育研修に反映させていくことで、パワハラ問題を許さない組織風土の定着を目指しましょう。
なお、引用の際は以下を明記ください。
出典:株式会社クオレ・シー・キューブHP
弊社のパワーハラスメント対策のノウハウをご活用頂くことによる5つの成果
-
1.行為の抑止パワハラ行為の抑止
-
 5つの成果
5つの成果 -
2.適切な指導伝えるべきことを伝える、上司の適切な指導
-
3.誤解の抑制パワハラと誤解しているケースの抑制
-
4.実践の促進従業員一人一人の実践による職場づくり
-
5.知見の蓄積パワハラ対策に関する社内の体験や知見の蓄積
クオレの6つの特徴
-
1.カスタマイズ提案
職場の状況やご要望に応じて、お客様独自のカスタマイズプランをご提案
-
2.豊富な経験と実績
年間約750件の研修実績とのべ3000社以上のコンサルティング実績
-
3.パワハラ対策の第一人者
パワハラという言葉の発案・定義して以来、ハラスメント対策のパイオニアとして多種多様な業種、業態の状況を熟知
-
4.中立的な視点
被害者と企業のどちらかに偏ることなく、中立的な視点で企業と従業員が共に成長できるためのアプローチを支援
-
5.専門家集団
企業経験がある産業カウンセラー有資格者が相談員。経験豊富な講師陣。弁護士、社労士と連携
-
6.高い評価と信頼
大企業から中小企業、行政などからのリピートオーダー多数。厚労省委員等にも度々就任。
職場のパワハラ、なぜ起こる?
職場のパワハラは、そもそも職場で働いている者同士の間にある「パワーの差」から生まれると言えるでしょう。地位の上下、能力の高低、経験の有無などの差は、それぞれが優位性・劣位性を感じ、優越感・劣等感を抱くところにパワハラのきっかけがあります。
その「差」に基づく、個の尊厳否定、多様性の否定、能力・成長の否定などがパワハラに発展する可能性を含んでいるため、職場の誰もが行為者にも被害者にもなりうるのです。
パワハラのきっかけ
- 役職・職位の上下
- 能力の高低
- 経験の有無 等によって生じる「差」によって発生
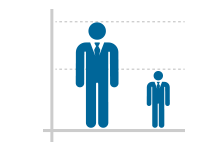
パワハラ行為の背景となるもの
- 個の尊厳否定
- 多様性の否定
- 能力・成長の否定

求められる対策
職場には、適切な組織管理を実行するためのパワーが必要ですが、そのパワーがパワハラの源泉となり得るため、どのような業種で職場でもパワハラが起きてもおかしくありません。
ハラスメント問題を放置すると・・・
- 社員の働く意欲の低下
- 優秀な人材の流出
- 労働紛争・不正・事故
- 社会からの信頼失墜
- 生産性の低下
- 人材確保の難航
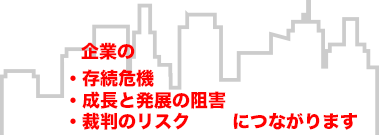
労働施策総合推進法において、職場におけるパワーハラスメントについて事業主に防止措置を講じることを義務付けています。健全な企業運営と成長のためにも欠かせない責務であると認識して、パワハラ対策に取り組みましょう。
ハラスメント対策の専門家にお任せください
パワハラの専門知識がないと・・・
- 不当な懲戒処分
適正な指導を行った管理職をパワハラで懲戒処分してしまう - 裁判に発展
重大なパワハラ問題を「よくあること」と見逃してしまい、裁判に発展 - うつ状態が悪化
メンタル不調者のパワハラ調査を進めた結果、うつ状態が悪化 - 予防意識の希薄
教育研修を実施したものの、パワハラ予防の意識が定着しない
フォームからのお問い合わせ
他のサービスはこちら

ハラスメント・コンサルティング
近年頻発しているパワハラ関連のニュースなどによってパワハラはいまや社会問題となっています。パワハラが被害者に与える心理的ダメージ、その結果企業が背負わなければならない企業イメージの低下、優秀な人材の流出、生産力の低下など、パワハラが企業へ与えるダメージの大きさは残念ながら想像にたやすいと言わざるを得ません。

セクハラ対策
男女雇用機会均等法が施行されて以来、セクハラ(セクシャルハラスメント)に関する知識は教育研修等でかなり浸透していると思われますが、一方で「セクハラ被害を受けた」という相談は減少していません。被害者も、女性ばかりではなく男性の被害も増える傾向にあります。

マタハラ・ケアハラ対策
2017年の法改正により、マタニティハラスメント、およびケアハラスメントの防止についても措置義務化され、管理職のみならず同僚同士、女性同士のハラスメントについても企業の責任が問われています。

カスハラ対策
BtoBカスハラ対策のポイントは、自社の従業員がカスハラ被害に遭った場合、会社としての対応を万全にすることです。企業は、トップからのメッセージや研修などを通じてその姿勢を社内外に示すことで、カスハラ被害を未然に防ぎ、自社員によるカスハラ行為を防止します。

ハラスメント防止・予防対策
昨今、ハラスメント問題は、ニュースなどで取り上げられないことがないほど、珍しくない現状となりました。このことは、いつ職場でハラスメント問題が発生してもおかしくない、とも言えます。

ハラスメント相談体制強化のためのサービス
2017年1月から、マタハラやケアハラについても事業主に措置義務が課されることになりました。また、事業主が講ずべき措置には「その他のハラスメント相談と一元的に受け付け、対応することが望ましい」とされ、企業のハラスメント相談窓口の適切な対応が重要になっています。

ハラスメント問題対応
ハラスメント問題は、どれだけ予防に尽力していても、絶対に起きないとはいえません。万が一起きた場合に備え、その対応策を万全にしておくことは企業のハラスメント対策を推進するうえでの安心につながります。問題が起きたことよりも、その問題への対応により、従業員・取引先・顧客を含め、社会の企業に対する信頼度は強まったり揺らいだりするものです。

女性活躍推進・ダイバーシティ対策の概要
今や企業の成長と発展に不可欠な要素となった、企業のダイバーシティ対策。 その中心的な役割を担っているのが、女性活躍推進施策です。301人以上の企業は、女性活躍推進法により、女性の活躍の場を広げる施策を具体的に策定することが求められています。

性的マイノリティ対策
2017年1月1日より、性的マイノリティ(LGBT/SOGI)へのセクハラ発言も、措置義務が課されるようになりました。そのような中で、誰もが自分らしく生きられる、能力発揮ができ、企業、そして社会に貢献できる職場をつくるために、お客様が直面する様々な課題にお応えしています。

コンプライアンス対策
2017年3月、消費者庁より「公益通報者保護法」ガイドラインが改正されました。企業の存続を脅かすコンプライアンス問題を早期に発見・解決するためにも、内部通報を放置しないような体制づくりや通報内容など秘密保持の徹底、通報内容の透明性などが強化され、企業にも通報制度の周知や教育を促進することなどが推奨されています。

社外相談窓口
どんな職場にもトラブル発生の可能性は潜んでおり、働く人たちの悩みはつきないものです。大ごとにしたくないという気持ちや雇用不安などから、社内では相談しづらいという人も多く、問題を深刻化させてしまいます。

ハラスメント研修
長年ハラスメント問題を調査・研究し、1999年からセクシュアルハラスメント研修、2003年からパワーハラスメント研修を行ってきたこれまでのノウハウを活かし、職場の状況や、ハラスメント防止対策の推進段階に合わせた研修内容のご提案をしています。

行為者行動変容プログラム
パワハラ行為者(加害者)の行動変容を促すサービスです。ハラスメントリスクが高いと思われる管理者に、予防として実施することも効果的です。

個別面談プログラム
受講者が自分自身を知ることを促す「内省型のオンラインプログラム」です。仕事の流れや考え方・行動などを客観的に振り返り、見つめ直すことで、これまでの自分自身に気がつき、自分を知るきっかけにしていただきます。

職場環境調査(アンケート/ヒアリング)
職場環境調査(アンケート/ヒアリング)によって組織の実態を把握し、現場の声をハラスメント防止策として職場づくりに具体的に生かすことはとても重要です。それぞれの企業の状況に合ったハラスメント対策が可能になります。

事実調査ヒアリング代行
パワハラ等が発生した際に、客観的な立場でヒアリングを行い、クライアント企業様の適切な対応を実務的にサポートいたします。

ハラスメント対策チェック
自社のハラスメント対策の現状を把握し、今後取り組むべき施策のみならず、何から手を付けるべきか、その優先順位もお伝えすることで、ハラスメント対策担当者の取り組みをご支援いたします。
